若手プロセスケミストのBocです。
今日は会社に入ってプロセスケミストになってから学んだ有機化学実験のコツについてです。
大学時代で最低3年みっちり実験してきた自負はあったのですが、まだまだ知らないことは多いわけでして…
雑学程度に「ふーん」って読んでもらえれば幸いです。
今回は溶媒編です。
学生の頃に湯水のように使っていたあれこれ、実はプロセスケミスト視点では「う~ん…」ってものがほとんどなのです。
ヘキサンは静電気を帯びるので製造では避けたい
学生の頃に使用していたNo.1溶媒、ヘキサン
製造ではできれば避けたいです。
その意外な理由が、なんと静電気!!
ヘキサンは導電性が高い≒静電気が発生しやすい溶剤です。
さらに引火点が-22℃と非常に低いです。
これらは火災の原因となります。
同様にアセトン、トルエン等も静電気が発生しやすいので気を付けましょう。
ちなみに製造装置の洗浄はアセトンではなくメタノールだったりします。
酢酸エチルは避けたい、できればイソプロピル酢酸
酢酸エチルは加水分解しやすいです。いわれてみればエステルだもんな……という気はしますが、そんなこと今まで誰が気にしていたでしょうか。
プロセスでは0.1%の不純物すら管理を求められる世界です。加水分解された酢酸エチルが微量でも基質と反応してしまった、加水分解によって生成したエタノールや酢酸などの残留溶媒試験が増えた、なんてトラブルの種になりかねません。分液中に製造装置のエラーでそのまま数日放置されてしまったら…考えたくもありません。
そんなわけでよりかさ高く分解が相対的に生じにくいイソプロピル酢酸に代替されるケースが多いです。
クロロホルムは嫌がられる
ICH M7というガイドライン中があるのですが、その中に残留溶媒の規定があります。
クロロホルムは非常に規制が厳しいので、可能な限りジクロロメタンで代用します。
ジクロロメタンでも国内では嫌がられやすい、らしいのですが、海外なら抵抗なく製造に使用するイメージです。
ハロゲンを含む溶剤は(1,2-ジクロロエタン、四塩化炭素なども)毒性が高いので使いたくない!と覚えてしまってまずはオッケーです。ジクロロメタンはしぶしぶ使う感じですねー
ちなみにケミスト見習いの諸君へ、コナン君によく出てくるシーン、クロロホルムで気絶する!は現実的には起こりません。安心して(?)ください。
THFはbrineとならば分液できる、2-MeTHFは普通に分液できる
THFが水と混ざるのは常識!抽出には酢酸エチルとかクロロホルム入れなきゃ!とか思っていませんか?
実は水層の塩濃度が高いとTHFでも分液できちゃうのです。使いどころは?と聞かれると難しいのですが…
一方2-MeTHFでは分液が可能です。
メチル基がたった一つ増えるだけでこんなにも物性が変わるものなのですね。
学生の人にはあまりなじみのないこちらの溶媒、プロセスでは頻出で検討候補に入ります。
晶析前に分液を挟みたいときは反応溶媒をTHFから2-MeTHFに変更すること、なんてこともあります。
ちなみにTHFは酸性にて開環し、様々な不純物へと変換されるので、この点も覚えておいてください。
ジエチルエーテルはCPME、TBMEなどに変更
ジエチルエーテルはご存じのとおり揮発性が非常に高いです。沸点が34.6℃って真夏日のほうが温度が上です。引火点がー45℃、静電気が帯びやすい等の性質から火事の恐れもあります。
少し昔は代替品としてイソプロピルエーテルも使用されていたのですが、過酸化物ができやすいとのデータより、使用頻度は徐々に落ちてきています。近年ではCPME(シクロメチルペンテルエーテル)、TBME(tert-ブチルメチルエーテル)が主流かなーという印象です。
学生にはなじみがないかもしれませんね。
ちなみに私はCPME開発者の論文を読んだことがあります。(どや)
DMFはニトロソアミンが生じる
ニトロソアミン類(RR’-N-N=O)はDNA反応性を有し、発がんリスクのある化合物として知られており(変異原性)、ICH M7にて厳しい管理を求められます。
DMFと試薬や薬の中間体、原薬などが反応してニトロソアミンが生成する可能性が否定出来ません。
同様の理由でNMP、DMAなんかも注意が必要です。
かと言って非常に溶解性が高く、反応への使い勝手もよいのでついつい使いがちです。
使用する場合には、ニトロソアミン含有量を実際に測定したり、理論的に説明したり(パージファクターなど)、含有のリスクがないことを当局に説明します。
以上です。学生の頃王道だった溶媒たちにはこんな側面もあるんですね。
コメント、間違いのご指摘等あればどんどんお願いします。

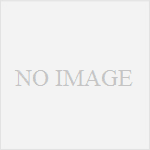
コメント